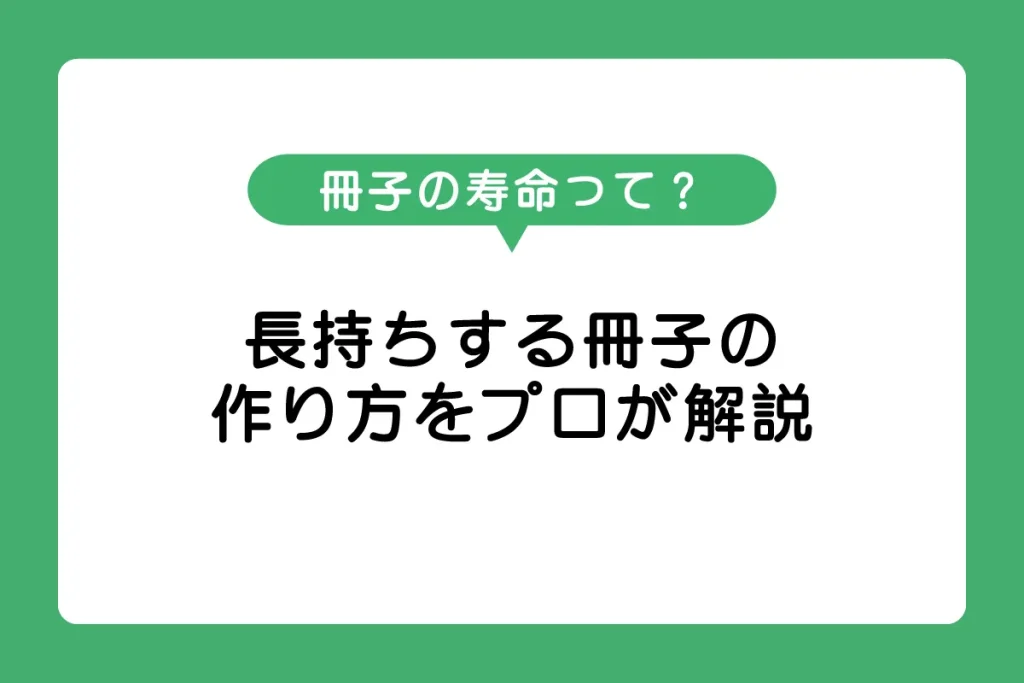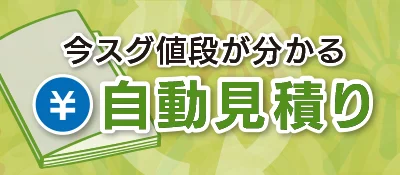製本方法によって冊子の寿命は変わります。長持ちする冊子の作り方をプロが解説。用途に合った製本方法を選択するよう意識しましょう。
製本方法で変わる冊子の寿命
冊子を作るとき、気になるのが「どれくらいの期間、きれいに使えるのか?」という点。これは、使用する製本方法によって大きく左右されます。以下では代表的な3つの製本方法の寿命と適した用途を解説します。
中綴じ(ホッチキス綴じ)
- 寿命の目安:半年〜1年
- 特徴:紙を二つ折りにし、真ん中をホチキスで留めるシンプルな製本。
- 耐久性:ページ数が少ない場合には問題ないが、厚みが増えるとページが外れやすくなる。
- 適した用途:学校の冊子、イベントパンフレット、短期配布用マニュアルなど。
長持ちさせるには用紙を厚めにすることで、開閉による劣化を抑える。
強引に開いて中央に無理な折り目がつかないよう注意。
無線綴じ(のり綴じ)
- 寿命の目安:1年〜3年
- 特徴:背を断裁し、糊で固めて表紙を巻く方式。
- 耐久性:日常的に開閉する用途には劣化しやすいが、一般的な冊子印刷では最も多く使われる。
- 適した用途:報告書、カタログ、商業冊子、マニュアルなど。
長持ちさせるには開き癖をつけすぎない(見開きに押さえつけすぎると糊が劣化しやすい)
湿度や温度管理に気をつける。
平綴じ(サイドステッチ)
- 寿命の目安:1〜2年
- 特徴:左側(または右側)の余白部分をホチキスや針金で留める方法。
- 耐久性:中綴じよりページ数に強く、ホチキス部分が開閉の力を受けにくい。
- 適した用途:学校資料、配布資料、短期保存の事務用冊子など。
長持ちさせるには左側の余白を十分にとって設計する。
ページ数が多すぎないようにする(40ページ以下推奨)
長持ちする冊子を作るためのポイントまとめ
| ポイント | 解説 |
|---|---|
| 綴じ方の選択 | 使用頻度や保存期間に応じて中綴じ/無線綴じ/平綴じを使い分ける |
| 用紙の厚み・種類 | 薄い用紙は劣化しやすい。厚紙やコート紙で補強するのがおすすめ |
| 使用状況を想定した設計 | 頻繁に開く場合は無線綴じ、軽量で配布用なら中綴じ・平綴じが最適 |
| 湿度・温度管理 | 高温多湿の場所では保管時に変形や劣化しやすいため要注意 |
用途に応じた製本選びで冊子はもっと長持ち
どの製本方法も「用途と予算に合った選び方」が重要です。中綴じや平綴じで十分な場合もあれば、無線綴じを選ぶことで耐久性を高めることもできます。モノクロドットコムでは、用途や予算に合わせて最適な製本方法をご提案しています。印刷物を長く美しく保つために、まずは製本の選び方からじっくり検討してみましょう。